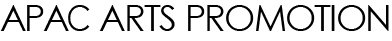東京ファンファーレオーケストラ第12回定期演奏会
2024年12月23日(月) 渋谷区文化センター大和田さくらホール
2024年12月23日(月) 渋谷区文化センター大和田さくらホール
映画『ハリー・ポッター』シリーズより
作曲:ジョン・ウィリアムズ (John Williams)
編曲:伊藤慶亮 (Yoshiaki Ito)
作曲:ジョン・ウィリアムズ (John Williams)
編曲:伊藤慶亮 (Yoshiaki Ito)
誰もがその音楽を聞くだけで、魔法と冒険の世界に入り込む感覚にさせる『ハリー・ポッター』シリーズのサウンドトラック。大作曲家ジョン・ウィリアムズが作り上げた魅惑の楽曲は、今日も世界中の音楽ファンを魅了し続けています。
本日はファンファーレオーケストラの稀有な響きで、そして曲によりサクソフォン・コアーやブラス・コアーの編成で、お楽しみください。
本日はファンファーレオーケストラの稀有な響きで、そして曲によりサクソフォン・コアーやブラス・コアーの編成で、お楽しみください。
1. 魔女、杖、魔法使い (『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』より)
Witches, Wands and Wizards (from The Prisoner of Azkaban)
この曲は、魔法界の神秘的な雰囲気と魔女や魔法使いの存在を、音楽で鮮やかに描いています。フリューゲルホルンの柔らかく重厚な響きが、魔法の杖の動きや呪文の不思議さを巧みに表現しています。また、緊張感と高揚感が絶妙に交差し、ハリーが魔法の世界で経験する驚きや興奮が聴衆に伝わります。
Witches, Wands and Wizards (from The Prisoner of Azkaban)
この曲は、魔法界の神秘的な雰囲気と魔女や魔法使いの存在を、音楽で鮮やかに描いています。フリューゲルホルンの柔らかく重厚な響きが、魔法の杖の動きや呪文の不思議さを巧みに表現しています。また、緊張感と高揚感が絶妙に交差し、ハリーが魔法の世界で経験する驚きや興奮が聴衆に伝わります。
2. 夜の騎士バス (『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』より)
The Knight Bus (from The Prisoner of Azkaban)
「夜の騎士バス」は、迷子の魔法使いを乗せる魔法のバスのテーマ曲です。軽快なリズムと独特のジャズ調の音楽が特徴で、バスのコミカルで奇想天外な動きが見事に描写されています。複雑に入り組む旋律や多彩なパーカッションの音が、忙しなく揺れるバスの様子やカオスを表現しています。
The Knight Bus (from The Prisoner of Azkaban)
「夜の騎士バス」は、迷子の魔法使いを乗せる魔法のバスのテーマ曲です。軽快なリズムと独特のジャズ調の音楽が特徴で、バスのコミカルで奇想天外な動きが見事に描写されています。複雑に入り組む旋律や多彩なパーカッションの音が、忙しなく揺れるバスの様子やカオスを表現しています。
3. ギルデロイ・ロックハート (『ハリー・ポッターと秘密の部屋』より)
Gilderoy Lockhart (from The Chamber of Secrets)
ギルデロイ・ロックハートは、その自己顕示欲とお調子者ぶりで観客に笑いを提供するキャラクターです。この曲は、彼の派手な性格と隠された滑稽さを音楽で見事に描いています。彼の自信満々な態度と同時に、背後に漂うどこか空虚な雰囲気も感じさせます。ユーモアと皮肉が交錯する一曲です。
Gilderoy Lockhart (from The Chamber of Secrets)
ギルデロイ・ロックハートは、その自己顕示欲とお調子者ぶりで観客に笑いを提供するキャラクターです。この曲は、彼の派手な性格と隠された滑稽さを音楽で見事に描いています。彼の自信満々な態度と同時に、背後に漂うどこか空虚な雰囲気も感じさせます。ユーモアと皮肉が交錯する一曲です。
4. ニンバス2000 (『ハリー・ポッターと賢者の石』より) ※サクソフォン・コア-
Nimbus 2000 (from The Sorcerer's Stone) *saxophone choir
「ニンバス2000」はハリーが初めて手に入れる魔法の箒(ほうき)であり、その滑らかな飛行を音楽で表現した曲です。サクソフォンの柔らかくも澄んだ音色が、空を自由に舞う軽やかさと風を切るスピード感を生み出します。音楽が徐々に高揚し、観る者を空高く引き上げていくような感覚が楽しめます。
Nimbus 2000 (from The Sorcerer's Stone) *saxophone choir
「ニンバス2000」はハリーが初めて手に入れる魔法の箒(ほうき)であり、その滑らかな飛行を音楽で表現した曲です。サクソフォンの柔らかくも澄んだ音色が、空を自由に舞う軽やかさと風を切るスピード感を生み出します。音楽が徐々に高揚し、観る者を空高く引き上げていくような感覚が楽しめます。
5. クィディッチ (『ハリー・ポッターと賢者の石』より) ※ブラス・コア-
Quidditch (from The Sorcerer's Stone) *brass choir
魔法世界の架空のスポーツ「クィディッチ」の試合の興奮とスリルを、ブラスの力強い音楽が余すことなく表現しています。ホルンやトランペットの鋭い音色が選手たちの激しい競争を表し、試合のスピード感と緊迫感が伝わります。まるで自分も試合の中にいるかのような臨場感に包まれる一曲です。
Quidditch (from The Sorcerer's Stone) *brass choir
魔法世界の架空のスポーツ「クィディッチ」の試合の興奮とスリルを、ブラスの力強い音楽が余すことなく表現しています。ホルンやトランペットの鋭い音色が選手たちの激しい競争を表し、試合のスピード感と緊迫感が伝わります。まるで自分も試合の中にいるかのような臨場感に包まれる一曲です。
6. ハリーの不思議な世界 (『ハリー・ポッターと賢者の石』より)
Harry’s Wondrous World (from The Sorcerer's Stone)
この曲はハリー・ポッターの世界観を象徴するテーマ曲であり、シリーズ全体を通して最も印象的な楽曲のひとつです。壮大なオーケストレーションと美しいメロディーが、魔法の世界への入り口を開きます。フリューゲルホルンが繊細に物語を紡ぎ、ブラスセクションが冒険と勇気を力強く表現。映画の名シーンが目の前に広がるような、感動と躍動感に溢れる作品です。
Harry’s Wondrous World (from The Sorcerer's Stone)
この曲はハリー・ポッターの世界観を象徴するテーマ曲であり、シリーズ全体を通して最も印象的な楽曲のひとつです。壮大なオーケストレーションと美しいメロディーが、魔法の世界への入り口を開きます。フリューゲルホルンが繊細に物語を紡ぎ、ブラスセクションが冒険と勇気を力強く表現。映画の名シーンが目の前に広がるような、感動と躍動感に溢れる作品です。
世俗カンタータ『カルミナ・ブラーナ』より
作曲:カール・オルフ (Carl Orff)
編曲:伊藤慶亮 (Yoshiaki Ito)
作曲:カール・オルフ (Carl Orff)
編曲:伊藤慶亮 (Yoshiaki Ito)
カール・オルフの代表作『カルミナ・ブラーナ』は、中世の歌詞を元にした世俗カンタータであり、力強いリズムとドラマチックな音楽が特徴です。全体を通して人間の欲望、運命、そして自然の美しさが描かれ、聴衆を圧倒するような壮大な音楽体験を提供します。特に「おお、運命の女神よ(O Fortuna)」は、その荘厳な響きで世界的に有名です。
本日は伊藤慶亮の編曲により、ソロやセクションフューチャー(*)を交えながら、この壮大な音楽にファンファーレオーケストラで挑戦致します。
本日は伊藤慶亮の編曲により、ソロやセクションフューチャー(*)を交えながら、この壮大な音楽にファンファーレオーケストラで挑戦致します。
1. おお、運命の女神よ (O Fortuna)
この作品は『カルミナ・ブラーナ』の冒頭と終結に配置され、運命の女神「フォルトゥナ」の気まぐれと力強さを歌い上げます。原曲では荘厳なコーラスと力強いオーケストレーションが、運命に翻弄される人間の姿を壮大に表現し、圧倒的な音響効果で聴衆を魅了します。
この作品は『カルミナ・ブラーナ』の冒頭と終結に配置され、運命の女神「フォルトゥナ」の気まぐれと力強さを歌い上げます。原曲では荘厳なコーラスと力強いオーケストレーションが、運命に翻弄される人間の姿を壮大に表現し、圧倒的な音響効果で聴衆を魅了します。
2. 運命の女神の痛手を (Fortune plango vulnera) *バリトン・ユーフォニアムセクション
「おお、運命の女神よ」に続くこの楽章は、運命の無情さとその影響を嘆く歌です。力強いリズムが運命の冷酷さを際立たせ、歌詞に込められた悲痛な叫びが音楽に反映されています。
「おお、運命の女神よ」に続くこの楽章は、運命の無情さとその影響を嘆く歌です。力強いリズムが運命の冷酷さを際立たせ、歌詞に込められた悲痛な叫びが音楽に反映されています。
3. 春の愉しい面ざしが (Veris leta facies) *サクソフォンセクション
春の訪れと自然の美しさを讃える楽章です。明るい音楽と軽やかなメロディーが春の息吹を感じさせ、生命の喜びと自然の再生を祝福します。
春の訪れと自然の美しさを讃える楽章です。明るい音楽と軽やかなメロディーが春の息吹を感じさせ、生命の喜びと自然の再生を祝福します。
4. 万物を太陽は整えおさめる (Omnia Sol temperat) バリトンソロ:山戸宏之
この楽章は、太陽が万物を平等に照らし、自然を統べる姿を描いています。穏やかな旋律と穏やかなハーモニーが、自然の調和と永遠のサイクルを讃えます。
この楽章は、太陽が万物を平等に照らし、自然を統べる姿を描いています。穏やかな旋律と穏やかなハーモニーが、自然の調和と永遠のサイクルを讃えます。
5. 見よ、今は楽しい (Ecce gratum) *サクソフォンセクション
春の喜びと若者たちの幸福感が表現された曲です。軽快なリズムと明るい歌声が、心躍る春の季節を生き生きと描き出します。
春の喜びと若者たちの幸福感が表現された曲です。軽快なリズムと明るい歌声が、心躍る春の季節を生き生きと描き出します。
6. 踊り (Tanz)
原曲もコーラスなしの楽章で、ダンスのリズムが印象的です。中世的な雰囲気を醸し出しながらも、力強いビートが音楽に活力を与えます。
原曲もコーラスなしの楽章で、ダンスのリズムが印象的です。中世的な雰囲気を醸し出しながらも、力強いビートが音楽に活力を与えます。
7. 森は花咲き繁る (Floret silva nobilis) *フリューゲルホルンセクション
この曲は、自然の美しさと春の喜びを讃えるものです。優雅な旋律と透明感のあるハーモニーが、森の花々や木々の息吹を感じさせます。
この曲は、自然の美しさと春の喜びを讃えるものです。優雅な旋律と透明感のあるハーモニーが、森の花々や木々の息吹を感じさせます。
8. 小間物屋さん、色紅を下さい (Chramer, gip die varwe mir) *ソプラニーノ&ソプラノサクソフォン
恋の喜びや美しさを求める若者の姿を描いています。リズミカルで軽やかな音楽が、歌詞の中の恋愛の高揚感や切なさを際立たせます。
恋の喜びや美しさを求める若者の姿を描いています。リズミカルで軽やかな音楽が、歌詞の中の恋愛の高揚感や切なさを際立たせます。
10. たとえこの世界がみな (Were diu werlt alle min)
この楽章では、全てを手に入れても愛には敵わないという思いが表現されています。力強く情熱的な音楽が、人間の欲望と愛の深さを描きます。
この楽章では、全てを手に入れても愛には敵わないという思いが表現されています。力強く情熱的な音楽が、人間の欲望と愛の深さを描きます。
11. 胸のうちは、抑えようもない (Estuans interius) バリトンサクソフォンソロ:西尾貴浩
内なる情熱と抑えきれない欲望を激しく歌い上げる楽章です。ドラマチックな展開と情熱的な歌声が特徴です。
内なる情熱と抑えきれない欲望を激しく歌い上げる楽章です。ドラマチックな展開と情熱的な歌声が特徴です。
12. 昔は湖に住まっていた (Olim lacus colueram) バリトンソロ:神山剛央
ユーモラスかつ風刺的な内容で、湖に住んでいた白鳥が食卓に出される運命を歌います。音楽は滑稽さと悲哀を巧みに表現しています。
ユーモラスかつ風刺的な内容で、湖に住んでいた白鳥が食卓に出される運命を歌います。音楽は滑稽さと悲哀を巧みに表現しています。
13. わしは僧院長さまだぞ (Ego sum abbas) ユーフォニアムソロ:深石奏生
この楽章は、酒場での僧院長の豪放な態度と騒々しい宴を描いています。陽気で軽妙なリズムが、酒場の賑やかな雰囲気を盛り上げます。
この楽章は、酒場での僧院長の豪放な態度と騒々しい宴を描いています。陽気で軽妙なリズムが、酒場の賑やかな雰囲気を盛り上げます。
14. 酒場に私がいるときにゃ (In taberna quando sumus) *フリューゲルホルンセクション
酒場での乱痴気騒ぎを描いた楽章で、力強いコーラスとリズミカルな音楽が特徴です。中世の宴会の熱狂が感じられます。
酒場での乱痴気騒ぎを描いた楽章で、力強いコーラスとリズミカルな音楽が特徴です。中世の宴会の熱狂が感じられます。
15. 愛神はどこもかしこも飛び回る (Amor volat undique) ソプラニーノサクソフォンソロ:小澤瑠衣
愛の神が至るところに存在し、恋心を煽る様子を歌います。繊細で優美な旋律が、愛の美しさと儚さを表現しています。
愛の神が至るところに存在し、恋心を煽る様子を歌います。繊細で優美な旋律が、愛の美しさと儚さを表現しています。
23. とても、いとしいお方 (Dulcissime) ソプラノサクソフォンソロ:松下洋
この楽章は、恋人への愛と献身を美しい旋律で歌い上げます。繊細で甘美な音楽が、純粋な愛の感情を表現しています。
この楽章は、恋人への愛と献身を美しい旋律で歌い上げます。繊細で甘美な音楽が、純粋な愛の感情を表現しています。
24. アヴェ、この上なく姿美しい女 (Ave formosissima)
美しい女性を称賛する楽章であり、原曲では力強い合唱と輝かしいオーケストレーションが印象的です。壮大なクライマックスへの序章となっています。
美しい女性を称賛する楽章であり、原曲では力強い合唱と輝かしいオーケストレーションが印象的です。壮大なクライマックスへの序章となっています。
25. おお、運命の女神よ (O Fortuna)
最初の楽章に戻り、壮大なフィナーレを迎えます。「O Fortuna」は人間が運命に翻弄される姿を象徴し、迫力ある合唱とオーケストラの響きで締めくくられます。
最初の楽章に戻り、壮大なフィナーレを迎えます。「O Fortuna」は人間が運命に翻弄される姿を象徴し、迫力ある合唱とオーケストラの響きで締めくくられます。